植物は動かない存在だと思われがちですが、実は太陽の動きに合わせて葉を上下に動かしているのをご存知でしょうか?
これは「光周性運動(こうしゅうせいうんどう)」と呼ばれる仕組みで、特に日光が大好きな植物ほど活発に見られる特徴です。
今回は、この植物の不思議な運動について、科学的な仕組みとともに詳しく解説します。
光周性運動とは?

光周性運動(Photonastic movement)とは、植物が太陽の角度に応じて葉の向きを変える運動のこと。
主に以下のような植物で観察されます。
- ホウレンソウ
- ヒマワリ
- クローバー
- カタバミ
これらの植物は、日中の光を最大限に受けるために、朝と夕方で葉の角度を変えているのです。
どうやって葉が動くの?
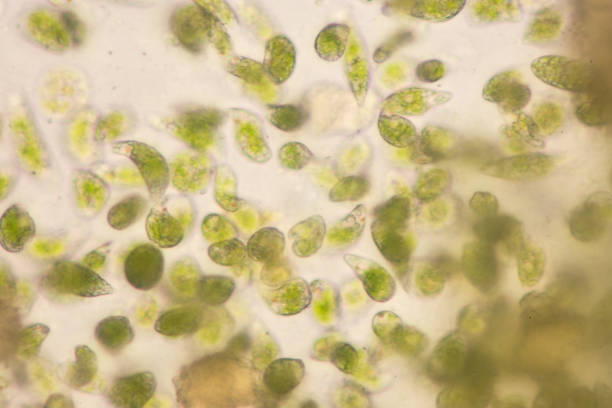
葉の根元には「葉枕(ようちん)細胞」と呼ばれる特殊な組織があります。
この細胞が水分の出入りをコントロールすることで、まるで筋肉のように葉の角度を微調整しているのです。
- 朝:太陽が昇ると、葉が上を向いて光をキャッチ
- 日中:広がって光合成効率を最大化
- 夕方:日が傾くと葉が角度を変えて追従
この運動は重力や風とは無関係で、光だけを手がかりにしている点が特徴です。
なぜ動く必要があるの?

この運動には大きく分けて2つのメリットがあります。
- 効率的な光合成
→ できるだけ多くの光を受け取ることで、エネルギー生産量が最大化されます。 - 過剰な光からの保護
→ 真夏の直射日光などでは、葉が角度を変えて葉焼けを防ぐ働きもあります。
植物ごとに個性が出る?

面白いことに、日陰を好む植物にはこのような動きがあまり見られません。
つまり、光が好きな植物ほど、葉の動きが顕著になるというわけです。
まとめ|植物の静かな“空の追跡者”たち
葉を動かして太陽を追いかける姿は、私たちが普段気づかないだけで、植物が環境に敏感に反応している証拠です。
「動かない」と思っていた植物にも、実は“空を見上げるリズム”がある。
そう思って観察してみると、いつもの植物がちょっと違って見えてくるかもしれません。




コメント